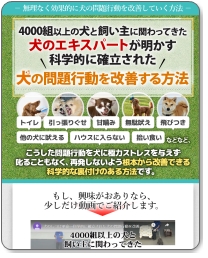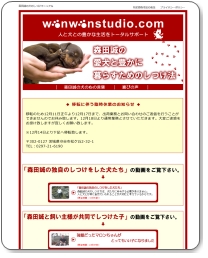犬の噛み癖のしつけ方|原因を正しく理解し愛犬と安心して暮らすための完全ガイド

犬の噛み癖に悩む飼い主さんは少なくありません。「甘噛みだから大丈夫」「そのうち治るだろう」と思っていたら、成犬になっても噛む行動が続いてしまった、というケースも多く見られます。噛み癖は放置すると事故やトラブルにつながる可能性があり、早めの対応がとても重要です。この記事では、犬が噛む理由を正しく理解したうえで、噛み癖のしつけ方をタイプ別に解説します。それぞれの対処法や、やってはいけないNG対応についても詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
噛み癖は、3つに分類する事ができる

噛み癖は、細かく3つに分類する事ができます。
- 「調査型」・・・新しいものを見つけると何でもとりあえず噛んでしまう
- 「遊び型」・・・相手との対象物の引っ張り合いなどで楽しむ
- 「攻撃型」・・・気に入らないと噛み付いてしまう
それぞれの噛み癖に対してしつけ方が異なります。詳しく見ていきましょう。
調査型の噛み癖のしつけ方|子犬に多い「確認行動」を正しく教える方法

「手を差し出すと噛む」「服の裾や指先をカプッとする」このような噛み方は、攻撃ではなく調査型の噛み癖である可能性が高いです。調査型の噛み癖は、主に子犬期に見られる行動で、世界を理解するための“確認行動”のひとつです。正しく対応すれば、大きな問題に発展することはほとんどありません。
調査型の噛み癖とは?
調査型の噛み癖とは、
- 軽く噛む
- すぐに離す
- 噛みながら様子をうかがう
といった特徴を持つ行動です。
犬にとって「噛む=手で触る」ような感覚であり、悪意や攻撃性はありません。
調査型の噛み癖が起こる原因
- 口で世界を学んでいる
- 好奇心が旺盛
- 人の反応を見ている
→犬は手が使えないため、口を使って物の硬さ・感触・安全性を確認します。
→新しい人、物、音に対して「これは何だろう?」という気持ちで噛みます。
→噛んだときに人が驚いたり、笑ったりすると、それが学習につながることもあります。
調査型の噛み癖の正しいしつけ方
- 過剰なリアクションをしない
- 触れてほしい行動を教える
- 噛めるおもちゃを常に用意する
→軽く噛まれても、騒がず冷静に手を引きます。大げさな反応は「面白い行動」と誤学習される可能性があります。
→噛まずに匂いを嗅げた、鼻でツンと触れた、という行動をしっかり褒めましょう。
→噛みたい欲求そのものは自然なため、噛んでよい対象を明確にします。
調査型でやってはいけないNG対応
- いきなり叱る
- 手を引っ込めて逃げる
- 口を押さえる
これらは不安や混乱を生み、逆効果になります。
遊び型の噛み癖のしつけ方|興奮コントロールがカギになる理由

「遊んでいると急に噛む」「テンションが上がると手を狙う」このようなケースは、遊び型の噛み癖が原因であることがほとんどです。遊び型の噛み癖は、エネルギーと興奮がコントロールできていない状態で起こります。
遊び型の噛み癖とは?
遊び型の噛み癖は、
- 興奮時に起こる
- 走り回りながら噛む
- 表情は楽しそう
という特徴があります。
悪意はありませんが、放置すると噛みが強くなりやすいタイプです。
遊び型の噛み癖の主な原因
- 興奮レベルが高すぎる
- 手を使った遊びが多い
- 発散不足
→特に若い犬や運動量の多い犬種に多く見られます。
→手でじゃらす、追いかける遊びは噛み癖を助長します。
→運動や刺激が足りないと、遊びの中で爆発します。
遊び型の噛み癖のしつけ方
- 噛んだ瞬間に遊びを終了
- 興奮しすぎない遊びを選ぶ
- クールダウンの習慣を作る
→「噛んだら終わり」を一貫して伝えます。静かに立ち上がり、その場を離れるのが効果的です。
→知育トイ、引っ張りっこ(ルール付き)、トレーニング遊びがおすすめです。
→遊び、休憩、落ち着く、という流れを毎回作りましょう。
遊び型でやってはいけないNG対応
- 興奮して追いかける
- 大声を出す
- 噛まれても遊び続ける
これらは「噛むともっと楽しい」と学習させてしまいます。
攻撃型の噛み癖のしつけ方|叱らず安全を最優先に考える対処法

唸る、威嚇する、出血するほど噛む。このような行動は、攻撃型の噛み癖に分類されます。攻撃型の噛み癖は、非常に慎重な対応が必要で、間違ったしつけは危険を伴います。
攻撃型の噛み癖とは?
攻撃型の噛み癖は、
- 明確な防衛・攻撃意思がある
- 唸りや歯を見せる行動を伴う
- 特定の状況で起こる
という特徴があります。
攻撃型の噛み癖の原因
- 恐怖・不安
- 資源防衛
- 痛み・体調不良
- 体罰や強制的なしつけ
→逃げ場がない、過去の怖い経験が引き金になることが多いです。
→食べ物・おもちゃ・寝床を守るための噛みです。
→体に触られたときだけ噛む場合は要注意です。
→過去の経験が原因で、人を信用できなくなっています。
攻撃型の噛み癖への対処法
- 噛む状況を徹底的に避ける
- 無理に触らない・近づかない
- 専門家と連携する
→噛む場面・人・行動を記録し、再現しないことが重要です。
→犬の「嫌だ」というサインを尊重します。
→ドッグトレーナー、獣医師(行動診療)にサポートをお願いする。
絶対にやってはいけないNG対応
- 力で押さえつける
- 威嚇し返す
- 叱って服従させようとする
- 自己判断で改善しようとする
これらは事故のリスクを高めます。
噛み癖タイプ診断チェックリスト|あなたの愛犬はどのタイプ?

原因を間違えると、しつけがうまくいかないだけでなく、噛み癖が悪化することもあります。まずは、愛犬の行動に最も近い項目をチェックしてみましょう。
【A】調査型の噛み癖チェック
- 指や手を軽く噛むが、すぐに離す
- 噛むときに力がほとんど入っていない
- 噛みながらこちらの反応をうかがう
- 初めて見る物・人に対して噛みやすい
- 子犬である
- 噛む前後で興奮していない
- 噛むというより「口で触っている」感じがする
 「はい」が多い場合
「はい」が多い場合
調査型の噛み癖の可能性が高いです。好奇心による確認行動で、深刻な攻撃性はありません。
【B】遊び型の噛み癖チェック
- 遊んでいる最中に噛むことが多い
- 興奮すると噛みが強くなる
- 走り回りながら手や足を狙う
- 噛むときの表情が楽しそう
- 運動不足の日ほど噛みやすい
- 手を使った遊びが多い
- 噛んでも遊びを続けると、さらに噛む
 「はい」が多い場合
「はい」が多い場合
遊び型の噛み癖の可能性が高いです。興奮コントロールと遊び方の見直しが必要です。
【C】攻撃型の噛み癖チェック
- 唸る・歯を見せるなどの威嚇がある
- 噛む前に明らかな緊張サインが出る
- 出血するほど強く噛んだことがある
- 特定の状況(触られる・近づくなど)で噛む
- 食べ物や物を守ろうとして噛む
- 噛んだ後も興奮や緊張が続く
- 叱るとさらに攻撃的になる
 「はい」が多い場合
「はい」が多い場合
攻撃型の噛み癖の可能性が高く、注意が必要です。自己判断でのしつけは危険な場合があります。